木田 裕也 院長の独自取材記事
Kクリニック
(豊中市/岡町駅)
最終更新日:2021/10/12
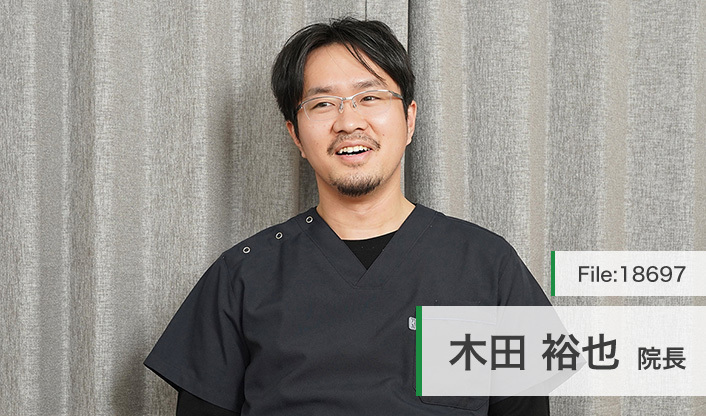
豊中市の住宅地に2018年開院した「Kクリニック」。バス通りに面しながら看板がないのは、がんの末期、再発患者に加え、輸血や人工呼吸器が必要な人など、重症の患者を中心に扱う在宅医療を専門とするクリニックだから。院長の木田裕也先生は、消化器のがんの手術に多く携わってきた日本外科学会認定の外科専門医だが、在宅でもレベルの高い治療を提供したいという思いからこの道に進んだ。「入院しなければいけないラインの見極めが大事」としながら、「しっかり評価をしてみたら、意外に在宅で対応できることが多いですよ」という木田先生。重症、難病の患者を診るための取り組みや、これからの北摂地域の在宅診療にかける思いについて聞いた。
(取材日2019年11月12日)
先進の医療で重症患者に対応、希望を持てる在宅診療へ
クリニックの特色はどんなところですか?

心電図、エコー、エックス線といったポータブル検査機器を充実させています。訪問診療では採血をするだけで、何かあれば入院をして検査をしなければいけないというところもありますが、ポータブル機器があれば在宅で診ることができます。また、在宅での診療で取り入れているところは少ないですが、難治性腹水に対するCART療法(腹水ろ過濃縮再静注法)にも対応可能です。たまった腹水を抜き、必要な栄養だけ残して体内に戻す治療で、緩和ケアの一つです。ただ、肝硬変に伴う腹水には適した治療法ですが、がん性腹水のある方は慎重にならなければならないなど、コントロールが難しい面もあります。タイミングや抜く量は人によって異なり、教科書はありません。保険適用の治療ですがハードルは高く、専門性の高い知識が必要となります。
難しい医療を在宅で取り入れているのはなぜですか?
がん末期の患者さんの中には、希望として抗がん剤治療をし続ける方もいますが、腹水の治療もそういった希望の選択肢の一つです。最終的には鎮痛剤などの量を増やしていくということが多くなりますが、こういうものがあると、症状の軽減を図ることができ、治療をしているという実感や希望を持っていただけると考えています。重症の方を診ているので、当然、24時間対応です。当院は看取りの実績などの条件を備えた「機能強化型在宅療養支援診療所」、そして末期がん患者を診る「在宅緩和ケア充実診療所」として診療を行っています。
幅広い範囲をカバーされることになりますね。

3次救急の病院での経験も豊富にあり、「これを見逃してはいけない」というものはわかっていたので、重症に移行しそうな症例の見極めにはそれほど困ることはありませんでした。一方、一般的な投薬の調整についてはわかりますが、治療抵抗性や難症例になると次の手がわからないこともあるので、特に循環器科、糖尿病内科、皮膚科、心療内科・精神科については専門の先生に加わってもらい、安心して治療を受けてもらえるように体制を整えました。また歯科とも連携しており、嚥下機能の評価が必要な患者さんを診てもらっています。若い医療者同士、連携して互いの質を上げていきたいと思っています。
家族にも寄り添い、こまやかな気遣いを
患者さんとの接し方で心がけていることはありますか?

ご本人とは会話ができないケースが多いのでご家族とお話しする機会が多くなります。重症の患者さんが多いので、ご家族には寄り添いながらも、どんなリスクがあって、今後どうなるかということを厳しめにお話しするようにしています。またいくら医療面では適切な在宅診療ができても、介護面で家族が大変で倒れてしまうこともあります。そういう場合は、ヘルパーさんを週に何回か入れてもらったり、入院したほうがいいですよと助言をしたりするようにしています。在宅で見ようというご家族は頑張り屋さんが多く、なかなかヘルプのサインを出せない方もいます。キーパーソンとなる方の表情はよく見るように注意していますね。
看護師との連携も求められますね。
はい。重症の方は訪問看護も活用してもらい、例えば医師が週に1回、看護師が週に3回ほど伺います。訪問看護師は、重症の患者さんに対しても適切にさまざまな手技をすることが求められ、ご家族に対してのケアもできるよう訓練を重ねています。より密にコミュニケーションをとるため、より重症に特化した訪問看護ステーションと連携をしています。「患者さんやご家族がこういうことを話していた」ということはしっかりフィードバックしてもらうようにしています。
もともと医師になられたのはどうしてですか? そもそもなぜ医師をめざされたのですか?

小学生の時、テレビで見た心臓の手術を見てかっこいいと思ったことがきっかけで、手術をしたくて医学部に入りました。かっこいいという憧れから志したのですが、実際にやってみると、想像していた一子相伝のような世界ではなく、今では教科書やビデオ教材も充実しています。手術の手技についてうまくなりたい一心で、寝ている時間以外は極力手術のことを考えイメージトレーニングをして、土日もラボで腹腔鏡の練習をするなど努力もしました。専門にしていた腹腔鏡カメラを使う手術では技術を磨き、手順を確実にこなしていく中で外科専門医の認定も取得し、外科で行われる難易度の高い手術を数多く執刀するようになりました。その中で、「外科医師は技術職。それよりもいろんなことを知っていて、いろんな病気を持っている患者さんを診られるほうが医師らしいのではないか」と思うようになりました。
栄養チームとの連携をめざし、患者により良い生活を
憧れの外科医師から在宅診療の道に進まれたのはなぜですか?

がんは手術をしても、転移や再発で治りきらないという患者さんが多くいます。そういった患者さんが抗がん剤も使えないようになると、今のわれわれのような在宅での療養や看護ケアに移るのですが、当時の僕は手術を行っても、その後患者さんがどのように過ごされているのか知りませんでした。そんな中、訪問診療のアルバイトで同行した施設で、がんの末期や再発の方の診察が十分に行われていない実態を目の当たりにしました。手術では術前術後も含め500ほどの手順を踏んでいるのに、その後のギャップに衝撃を受けました。在宅ではなかなか受けにくい輸血や酸素、点滴も、手術では当たり前の処置。在宅診療でこそほかの人にはできないような自分の力が発揮できるのではないかと、この道へ進みました。
今後の展望をお聞かせください。
現在は医科、歯科と連携して治療にあたっていますが、今後は理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、栄養士とも協力して集学的なリハビリチームや栄養チームを作ろうと考えています。嚥下機能が下がっている方の中には、食べられない方、食べられるけれども強引にペースト食を食べさせられているという方もたくさんおられます。そういった方の嚥下機能をしっかり評価した上で、食事形態やメニューを調整して、少しでも食べられるようにしたいですね。特にご高齢の方は食べることが楽しみの一つ。病院だとそういった栄養チームがあるのですが、在宅でそこまでしているところは少ないので、ぜひ取り入れていきたいと思っています。
読者にメッセージをお願いします。

「今の先生ではしっかり対応してもらえないので切り替えをしたい」というご相談を受けることもあり、悩んでおられるご家族や介護関係者の方がいらっしゃると感じています。今は病院からの紹介で在宅療養を利用される患者さんが多いですが、重症の方でも在宅療養ができるということを患者さんやご家族にも知ってもらいたいですね。「これだと在宅では無理かな」と思われていても、僕と看護師が伺って診てみると、意外に病院並みの対応ができることもあります。個別にお話ししてみないとわからない部分もあると思うので、お気軽に相談をいただければと思います。







